児童文学作家の角野栄子さん、幼年童話の作家を発掘
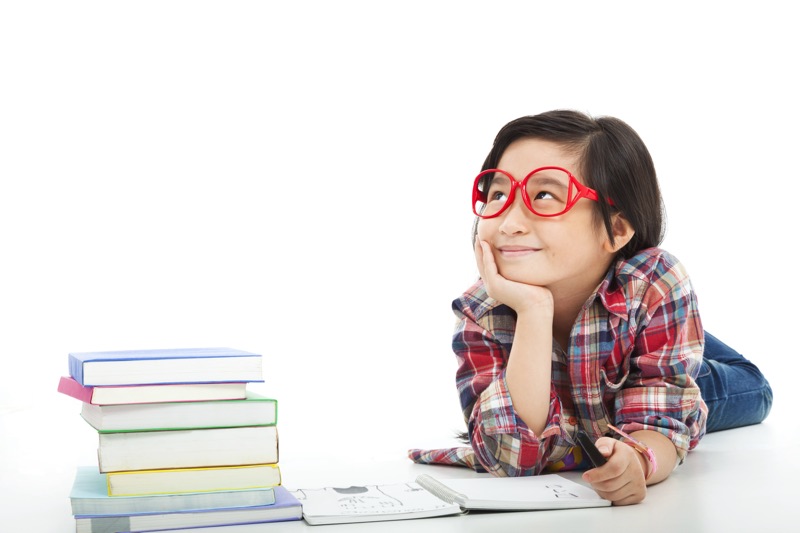
本を読み始めたばかりの子ども向けに、文章が少なく挿絵が多い童話は「幼年童話」と呼ばれます。
この分野で新たに活躍する作家を見出すことを目的に、昨年、「魔女の宅急便」などで知られる児童文学作家の角野栄子さん(90)らの発案により、新たな賞が設立されました。
その背景には、このジャンルが縮小しつつあるのではないかという強い危機感があるといいます。
(※2024年1月23日 朝日新聞の記事を参考に要約しています。)
幼年童話の未来をつなぐ取り組み
昨年11月末に行われた「角野栄子 あたらしい童話大賞」の贈呈式で、角野栄子さんはこう語りました。
「もっと評価されるべき幼年童話を、大人の世界が軽視しているのではないでしょうか」
角野さんは、幼年童話は絵本に親しんだ子どもたちが、文字の多い本へと移行するための「橋渡し」の役割を果たすと考えています。
自身も「魔女の宅急便」(1985年刊行)などの児童文学に加え、「おばけのアッチ」シリーズなど幼年童話の執筆を続けてきました。
「以前は幼年童話の作家がたくさんいました。
でも、寺村輝夫さんや古田足日(たるひ)さん、森山京(みやこ)さんといった方々が次々と亡くなられてしまって・・・」
さらに、「才能ある若い人たちは、より自由に創作できる絵本やマンガの世界に流れているのではないでしょうか」とも指摘します。
しかし、自由な発想は幼年童話の世界でも十分に生かせるはずです。
こうした思いから、作品を公募し、新たな作家を発掘する賞を創設することになりました。
その考えに幼年童話を出版するポプラ社も共感し、この賞が誕生したのです。
新たな才能が生み出す斬新な物語
昨年2月から5月末にかけて、商業出版されていない作品の公募が行われました。
大賞には、小学校の現役教員が手がけた作品が選ばれています。
物語の主人公は、熱を出して学校を休まなければならなくなります。
そんなとき、病気を預けたり引き出したりできるという「びょうき銀行」の不思議な看板を見つけるのです。
この独創的なストーリーが高く評価されました。
出版社では、より読みやすくするために作品をブラッシュアップし、挿絵を加えるなどして書籍化を目指しています。
今年も4月から新たな作品の募集が始まる予定です。
幼年童話の魅力と難しさ-つないでいくべき文化
1960年代から幼年童話を出版してきた児童書専門の「あかね書房」(東京)で編集を担当する加藤佳子さん(55)は、現在の状況についてこう語ります。
「絵本や小学校高学年以上向けの物語を書こうとする人は多い一方で、幼年童話に挑戦する作家は少ないのが現実です」
同社が手がける幼年童話は、400字詰め原稿用紙にして11~14枚ほどの分量で、大半のページに挿絵が入ります。
文字は基本的にひらがなを使用し、指でたどりやすい大きさに設定。
カタカナにはルビを振るなど、子どもが読みやすい工夫が施されています。
また、物語の導入部分で主人公に共感し、自然に物語の世界へ入り込めるかどうかも重視しているそうです。
「10枚ほどの短い文章で物語を成立させるのは難しいですが、一方で、読者が序盤からすぐに登場人物になりきれるのが幼年童話ならではの魅力です」と加藤さんは語ります。
あかね書房では、児童文学雑誌で見つけた作品の作家と連絡を取り、数年かけて幼年童話として単行本に仕上げることもあります。
「人生や哲学を盛り込んだ作品も多くあります。
こうした貴重な文化の火を絶やさぬよう、次世代へつないでいきたいですね」と、幼年童話への思いを語りました。
幼年童話の魅力。現実と物語の世界をつなぐ本
書店「丸善丸の内本店」で児童書を担当する兼森理恵さん(48)は、幼年童話について次のように考えています。
「現実の延長線上にあるような設定で始まり、自然に物語の世界へ入り込める。そして、読み進めるうちに新たな世界と出会える。そんな本こそ、幼年童話と呼ぶのにふさわしいと思います」
また、幼年童話には数多くの名作があることにも触れ、「子どもの成長には個人差があります。
小学校低学年を過ぎてから出会っても、決して遅いということはありません」と、その魅力が長く続くものであることを強調しました。
幼年童話の魅力と挑戦、子どもたちに安心と生きる力を届ける
2022年に初めて幼年童話の単行本を出版した香桃(かとう)もこさん(60)-愛知県-は、限られた語彙や文字数で表現することの難しさを感じながらも、その奥深い魅力に引き込まれています。
3人の子どもが幼い頃、絵本や童話を一緒に楽しんだ経験から、「子どもたちに安心感や生きる力を与えられるような物語を書きたい」と考えるようになりました。
そして約20年前、三重県にある児童書専門店が主催する童話作家志望者向けの「童話塾」に通い始めます。
さらに、児童文学雑誌への投稿も行い、審査員である作家から「幼年童話を目指してみては」と勧められたことをきっかけに本格的に挑戦。
そうして2022年、念願の単行本を出版するに至りました。
幼年童話の表現-子どもが感じる世界を言葉にする
幼年童話では、子どもが理解しやすい表現の工夫が欠かせません。
例えば、2024年に出版された単行本『わがしやパンダ』の序盤では、主人公の男の子が裏山で正体不明の生きものの気配を感じる場面に、次のような表現が使われています。
「あせが、きゅうにつめたくなって、せなかがぞくっとした」
単に「怖くてブルブル震えた」と書くのではなく、子どもが日常の中で実際に感じたことを想像しながら、言葉を慎重に選びました。
「物語を書き上げたとき、私の中の子ども心が喜ぶんです。だから、書くことをやめられません。1人で本の世界へ旅を始めたばかりの子どもたちに、物語の楽しさを伝えていきたいと思っています」と、著者は語ります。

