GIGAスクール構想でソフト面向上のための教職員の負担
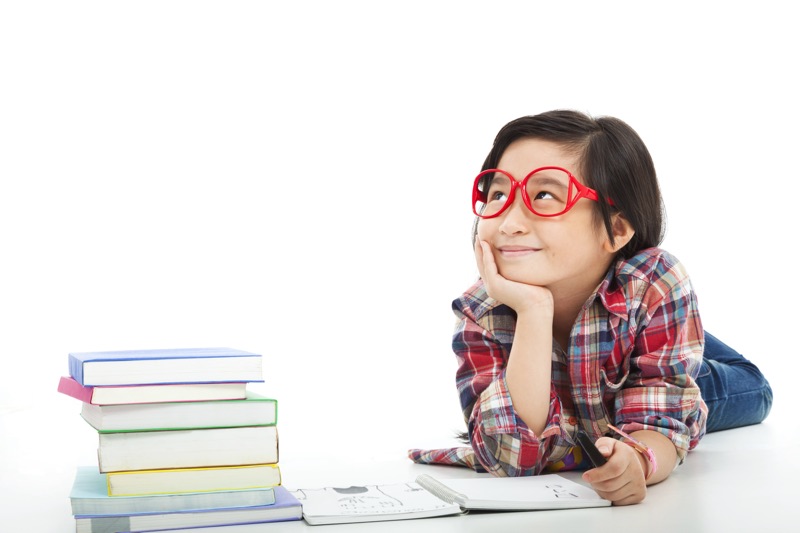
小中学生ひとり一台のコンピューター端末を配る「GIGAスクール構想」。
コロナ禍で本格導入が早められ、2年目となりました。
実際に端末は子どもたちに配備され、授業や長期休暇中の宿題などに活用されています。
学童保育所でもネット環境の調整などに追われていますが、教職員の負担など課題が見えてきました。
目次
GIGAスクール構想で見えてきた課題
増える教職員の負担
「GIGAスクール構想」によってによって、できる子は先に進み、つまずいた子はその部分を深く学べるという一人ひとりに合った教材で学習ができると文科省は伝えています。
AI先生がフォローしてくれ、自分なりの学びを進めることで学力が上がるとのこと。
しかし、どのような場合も教師がまず教えた上での学習となります。
そのため、英語の必修化、プログラミング教育、道徳の教科化など次々と新たな仕事が増え、教員は一人ひとりの子どもたちに寄り添う余裕がなく、猛烈に忙しくなりました。
新学期にパソコンを使用するまでの手続きやIDやパスワードの管理、端末の破損対応やネット環境のトラブル対応、個人情報の管理など、これまでも忙しかったのにさらに時間外労働が増加したという教職員が少なくありません。
課題も多いけれどICT教育が悪いということを述べる教職員はほとんどいませんが、準備時間や研修がほとんどなく、自分自身の勉強も滞っているのに、授業の準備、授業から端末の修理対応、ネット環境の整備まで学校に丸投げであること、子どもへの悪影響を放置していることに関して不満が募り、教職員は疲弊しているのです。
一人ひとりの端末を把握できない
一人一台の端末を配布されていますが、現在はさほど持って帰って宿題をやるという機会がないとはいえ、夏休みなどの長期休暇中は端末を自宅にずっと置いているため1年間使うと子どもに寄っては端末をボロボロにしてしまうケースもあります。
保護者からクレームが来ることもありますが、よほど画面にヒビが入っていたり、キーボードなどが扱えない状態になっているなどでなければ公立小中学校で端末の買い替えは難しいでしょう。
また、授業中に生徒の画面を教師がすべて把握するのは難しいものです。
仮に授業中ゲームをしていたり、チャットをしていたりしてもわかりません。
基本的に副担任やICT担当職員が見回っているものですが、スワイプすればすぐに隠れてしまうのでカンタンにごまかせるでしょう。
せっかく教材が宝の持ち腐れになり、教師の話を聞いていない児童、生徒の把握もしづらくなります。
子どもへの悪影響
読み書き計算が疎かになる
インターネットで調べれば大概のことは出てきます。
調べたいことを図鑑や辞書で調べたり、詳しい人に話を聞いたりという情報収集をして、物事を考えるのは基本的なソーシャルスキルと言えるでしょう。
嘘や誇張があるインターネットの情報の中でいかに取捨選択をするかを小中学生に教えるのは難しいものですが、これが当たり前になってきます。
ICTを使えば何でもできるような錯覚が起きてしまいますが、文字を書けない、読めない子が自動変換、予測変換に頼ってばかりで覚えてしまうことは従来の教育で大切にされてきた「読むこと、書くこと、計算すること」が疎かになってしまうでしょう。
学校という集団学習の場で、一斉授業の力を育てる時間はなく、若手の教職員はICTに偏りがちになり、授業を行う力量の向上にまで頭が回りません。
もちろん読み書き計算に対するデメリットばかりでは無いですが、学校に丸投げして推進しても現場で取り残されてしまい、ICTを扱えなければと不安になるのは教職員だけでなく、子どもたちや保護者も同じなのです。
考えようとせず、辞書で調べるわけでもなく、宿題の答えを教えてくれる端末に頼っていてもなかなか記憶に定着しないでしょう。
楽な方に流れてしまうとなかなか不便な方に戻れなくなってしまいます。
そうなるといざ端末を持ち込めない場面で困る子が出てくるのです。
もちろんメリットはあります。特別支援学級などで教科書の文字を大きくして確認することで配慮が必要な子どもたちが音読をできるようになった、読み上げる機能を利用して教科書の文章を聞きながら読む練習ができるなどです。
便利なガジェットだからこそ、正しい使い方をするのが大切なのでしょう。
ネット依存
「文部科学省からは、1人1台端末を『このくらいの時間を取って使用してほしい』という具体的なお願いはしておりません。一方で、『個別最適な学び』と『協働的な学び』の一体的な充実など、教育の質を向上させるためGIGAスクール構想を推進しているところであり、その観点で1人1台端末を日常的・効果的に活用いただきたいと考えています」
と話すのは文科省の担当者。
つまり、日常的に端末を活用するように解釈できます。
そのため、日常的に使わせるために「タブレットを自宅へ持ち帰らせるように」と通知し、時間制限なく自由に使わせるという自治体の教育委員会がでてきました。
それを受けて一日中タブレットに向かっている子どもが出てきます。
学校から配布されたタブレットやパソコンによってお子さんがネット依存になってしまうという悪影響が出てきているのです。
ネット依存症は、成績不振や不登校につながる社会的な問題です。
心身が不健康な状態になるため、保護者の方の不安をあおり、クレームにも繋がりかねません。
教育目的のコンピューターの配布からネット廃人を生み出しては本末転倒になってしまいます。
文房具と同じツールとして利用する
まずはどのような授業を行うかでタブレットを活用するほうが有効と判断できれば使うと良いのです。
筆算の練習をエクセルのワークシートを使ってやってみたり、タブレットで撮影した朝顔の写真をもとにじっくり観察をして絵を描いたり。
そういったちょっとしたことからICT教育をカンタンに導入していけば、今子どもたちが本当に授業に参加しているかどうかを目を皿にして確認する必要もありません。
同じ様にワークブックやノート、教科書が端末に入っていると考えると学童保育所の職員も児童の学習の進め方を見守りやすいのではないでしょうか。




