子どものSNS、投稿する前に「6秒待つ!」
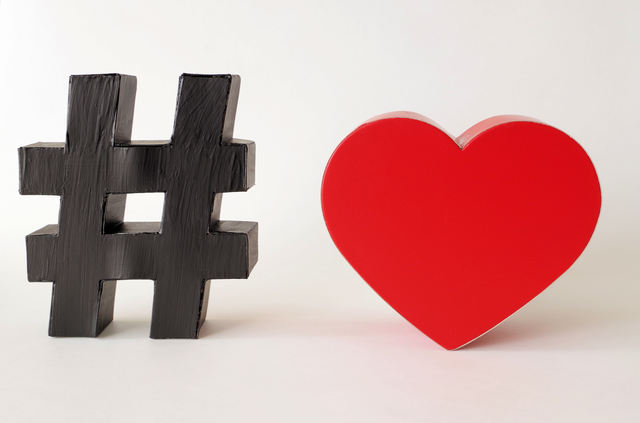
日本において、子どもたちによるSNSの利用は大きな関心事となっております。
現実には、多くの10代が日常的に利用している状況があり、リスクを抑えながら適切に関わるためには、どのような使い方が望ましいのでしょうか。
現在の若者がSNSをどのように活用しているのか、その実態を探るべく、若者の間で影響力を持つインフルエンサーや、情報セキュリティの専門家の意見を伺いました。
タレントでありモデルとして活動する22歳のみりちゃむさんは、SNSを使いこなすインフルエンサーの1人です。今回は、彼女のSNSの活用方法や考え方について、
「当たり前」のように使いながらも、常に注意を怠らない 投稿は時間をずらして/DMは開かない/トラブルは「距離を取る」
と語っています。
(※2025年3月30日 朝日新聞の記事を参考に要約しています。)
SNSとの付き合い方を考える-みりちゃむさんの実践と感じたこと
SNSを使い始めたのは、中学生の頃でした。
現在は、X(旧Twitter)、Instagram、TikTok、YouTubeを主に利用していますが、それぞれ異なる目的で使い分けています。
Xでは、思ったことをそのまま気軽に投稿しています。
Instagramでは、ファンに向けて仕事の合間のオフショットやプライベートの写真を発信しています。最近は、YouTubeで飼い猫の様子を紹介することが多くなっています。
情報を発信するだけでなく、SNSは私にとって情報収集の手段でもあります。
美容に関する話題など、以前は本で得ていたような知識も、SNSを通して得ることができます。
今では、調べ物をするときにも活用しており、食事をするのと同じくらい生活の一部になっています。
ただし、利用には細心の注意を払っています。
例えば、自宅周辺が写っているような写真は投稿しないようにしていますし、撮影後すぐには公開せず、時間を空けて投稿するようにしています。
また、ダイレクトメッセージで仕事の連絡が来ることもありますが、基本的には返信せず、やり取りは控えています。
不快なコメントを見かけたときには、深追いせずにブロックするようにしています。
また、過去には私に関することでファンが他の人に攻撃的な発言をしようとしたこともありました。
その際は、事前に「やめてほしい」と呼びかけました。
こうした対応は、誰かから教わったのではなく、活動を続ける中で自然と身についたものです。
私にとって、SNSは仕事の一部でもありますが、多くの若者は人とのつながりを求めて利用しているのではないでしょうか。
慎重に使おうという意識はあっても、興味や好奇心が勝ってしまうこともあります。
直接会って話すときには注意深くなるはずの感覚が、SNS上だとやや鈍くなるようにも感じます。
私は、SNSを開いたときに注意喚起の画面が出てくる仕組みがあれば良いと考えています。
ATMで「詐欺にご注意ください」と表示されるように、SNSでもリスクに対する情報や具体例が定期的に示されるようになれば、多くの人がより警戒心を持つのではないでしょうか。
トラブルを避けるためには、小さいうちから正しい使い方を身につけることが大切です。
ただ、親や教師のように「教える立場」の人が注意しても、子どもたちはあまり真剣に聞かないこともあります。
「注意されたけど、実際には問題なかった」という経験があると、なおさらです。
私自身、弟がいるのですが、親よりも私の言葉の方が響くようです。
そのため、SNSを日常的に使っている若者に近い世代がサポート役になることが重要だと思っています。
SNS投稿前に立ち止まる習慣を。花田経子さんが語る2つの大切な心得
子どもたちがSNSを利用する中で、どのような危険が潜んでいるのか、そしてそれにどう対処すべきか。
このテーマについて、慶応義塾大学大学院KMD研究所の花田経子さんが、日頃の講演活動の知見を基に「紙面講義」を行ってくださいました。
「本日は、ぜひとも心に留めておいていただきたいポイントが2つあります」と花田さんは語ります。
その1つ目が「6秒ルール」です。
投稿ボタンを押す前に、6秒だけ待つというシンプルなルールです。
感情が高ぶっているときほど、冷静な判断ができなくなり、誤った投稿をしてしまうリスクが高まります。
一度深呼吸をして、投稿内容を見直す時間を持つことが重要です。
SNS利用時に心がけたい5つの行動指針-花田経子さんが語るリスク回避術
花田経子さん(慶應義塾大学大学院KMD研究所)は、インターネットを利用する子どもたちが覚えておくべき基本的なルールとして、「インターネット5つの約束」を紹介しています。
(1)SNSなどで他人を傷つける言葉を投稿しないこと
(2)ネット上で知り合った相手に、自分の名前・住所・電話番号などの個人情報を伝えないこと
(3)インターネットで知り合った人に実際に会いに行かないこと
(4)他人のIDやパスワードを勝手に使わないこと、また自分の情報も誰かに教えないこと
(5)もし困ったことが起きたら、すぐに家族や信頼できる大人に相談すること
「特に最後の項目が最も重要です」と強調されます。
中学2年生の私の娘が、SNSのプロフィール画像に自宅のベランダから撮影した夕日の写真を使おうとしたのですが、私は止めました。
周辺の風景から自宅が特定される恐れがあるからです。
建物や背景から居住地域を推測されてしまいます。
皆さんのSNSにも、学校名や年齢などを書いていませんか?
学校名が記載されていれば通学範囲が、年齢やニックネームの組み合わせからは本人が特定される可能性があります。
SNSに投稿するさまざまな情報がつながることで、プライバシーの侵害につながるおそれがあるのです。
まるで玄関の鍵をかけるように、日頃から気をつけることが求められます。
ネット上の「知り合い」でも油断は禁物。写真や動画にも要注意
ある子が、オンラインゲームで仲良くなったAさんから『下着姿の写真を送って』と求められました。
嫌われたくなくて写真を送ってしまったところ、『会いに来て。断ったらこの写真をばらまくぞ』と脅されました。
誰にも相談できず、結局会いに行ってしまったそうです。この場合、どうするべきだったでしょうか?
知らない相手とは会わないようにすればいい、ということですか?
インターネット上で一度やり取りをした相手は、すでに“知っている人”と感じてしまいやすいのです。
ですから、『知らない人と会わない』ではなく、『ネット上で知り合った人と実際に会わない』というのが正確な表現です。
SNSやオンラインゲームなどを通じた誘い出しは、男女を問わず起こり得ます。
また、プライベートな部位が写っている写真や動画の撮影は絶対にやめてください。
たとえ自分自身で撮ったものであっても、法律に違反する行為と見なされる場合があります。
自分の身を守るためにも、慎重な行動が求められます。
いざという時のために、家庭でできるSNSの安全対策
SNSやインターネットを使う際には、情報を得る場としての便利さだけでなく、信頼できる大人や警察、公共機関が設ける相談窓口など、現実の支援体制を活用することがとても重要です。
家庭内で保護者ができることにはどのようなことがあるでしょうか。
「もちろん、保護者にできることはたくさんあります。最後に、それを皆さんへの宿題とさせてください」と花田さんは語ります。
(1)スマートフォンの使用時間や使う場所について
(2)SNSやメールで投稿する際に気をつけるルール
(3)困ったときに誰に相談するか
これらについて、ぜひご家庭で話し合ってみてください。
これは防災訓練と同じで、事前に話し合いをしておくことで、実際に問題が起きたときにも落ち着いて対応できるようになります。
子どもとSNSを考える第一歩は大人の理解から
子どもたちにとって、SNSは単なる交流の手段にとどまらず、情報を得たり共有したりする中で、自分の感性や創造性を育む場所にもなっています。
取材を通じて、SNSの持つ双方向性や情報発信の自由さが、彼らにとって大切な役割を果たしていることに気づきました。
こうした背景を踏まえると、単に子どもをSNSから遠ざけるのではなく、安全に使う方法を学ばせるほうが現実的で効果的だと感じます。
そのためには、まず身近な大人たちが、子どもたちが直面するリスクや課題についてしっかり伝えていく姿勢が求められます。
ただ、自分自身を振り返ると、今の子どもたちがどのSNSを利用しているのか、どう使っているのか、そしてどのような危険があるのかといった基本的な知識がまだ不十分だと痛感しています。
だからこそ、まずは大人自身がSNSに対する理解を深め、「どんな世界なのか」を知ることから始めていくことが重要だと感じています。

